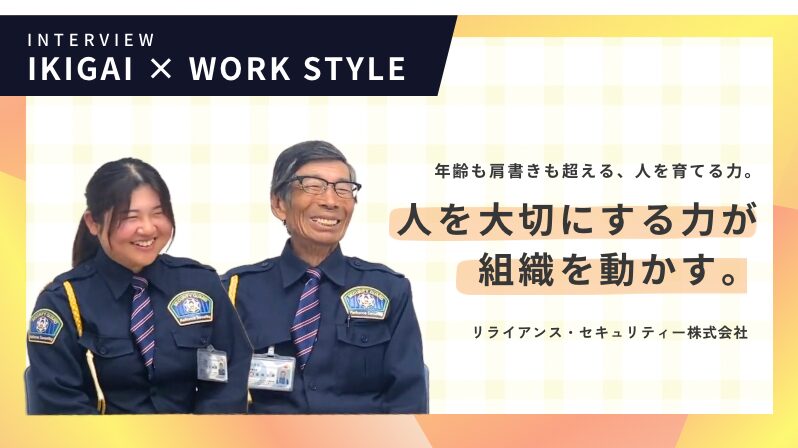壁をなくせば、人生は拓ける!変化を味方にする「幸せ選択」の極意(積水ハウス株式会社 山田 実和)
積水ハウス執行役員・山田実和さんのキャリアは、意図的ではなく「運の積み重ね」から偶発的に拓かれたと言います。目の前の仕事に真摯に向き合い、人との繋がりを大切にする中で、彼女は自身の働きがいだけでなく、「生きがい」をも見出す。この記事では、多様性を受け入れ、あえて楽観的に選択する彼女の哲学が、いかに働き方と人生観を豊かにするのかを探っていきます。

株式会社積水ハウス:山田 実和さん(執行役員 ESG経営推進本部長)
撮影場所:梅田スカイビル SEKISUI HOUSE Presents 絹谷幸二 天空美術館にて
1.偶然も必然も「目の前の仕事」にあり
――本日はお忙しい中、ありがとうございます。まず、実和さんの自己紹介と、これまでのキャリア、そして学生時代から現在に至るまでの仕事選びの考え方についてお聞かせいただけますか?
山田 実和さん(以下、実和さん):はい。積水ハウス株式会社 執行役員 ESG経営推進本部長の山田 実和です。本日はよろしくお願いいたします。
私自身のキャリアを振り返ってみると「これがやりたい」という明確な夢やビジョンを持って進んできたわけではありませんでした。今の10代や20代が若いうちから目標を掲げて努力する姿は本当に素晴らしいと感じますが、私自身はそうではありませんでした。
積水ハウスに入社したきっかけも父が建築関係の仕事をしていたことからのご縁が大きく、住宅業界への強いこだわりがあったわけではありません。ただ、当時の時代背景として、四年生大学卒の女性が働きやすく活躍できる会社であることは、私にとってのひとつの条件でした。入社後、たまたま配属されたのが、開発事業を手がける新しい部署で、約160名規模のとても印象的な職場でした。
――どんな部署だったのでしょうか?
実和さん:今で言う「ダイバーシティな職場」でした。社会人経験のある方、女性の総合職も多く、元教師や法律関係の専門職など、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が集まっていました。
個性たっぷりの混沌とした職場でしたが、それがかえって活気とエネルギーを生み出していて大企業でありながら、スタートアップのような自由な雰囲気の中で、私は様々な経験をさせてもらいました。

―― まさに、そういった多様な環境が、実和さんのキャリアの原点となったのですね。
実和さん:そうですね。私のキャリアは、振り返ると、意図的に計画したというよりも、まさに「運の積み重ね」によって築かれてきたと感じています。「これをやってみないか」と声をかけてもらい、それを自ら選び、目の前の仕事に一生懸命取り組んできた先に次の道が開けてくる、という繰り返しでした。
私は、一般事務職として入社しましたが、上司からさまざまな仕事を任され、実際には職務を超えて「右腕」として多様な業務に携わっていました。その後、分譲マンションの営業をきっかけに総合職へと転換しました。
―― 目標を明確に設定するよりも、目の前の仕事に集中することで道が拓かれてきたのですね。その「目の前の仕事で何ができるか」「自分の役割は何か」という問いかけが、実和さんの強みを見つけるヒントになったのでしょうか?
実和さん:まさにその通りです。自分の強みや価値を見つけるヒントは、会社に入ってから見つけたというより、学生時代の経験が大きかったと思います。
私は学生の頃から、人からよく相談を受けることが多く、その問題を解決して皆が喜んでくれることにやりがいを感じていました。人との繋がりを大切にする仕事がしたいという思いも強かったですね。営業の仕事では、お客様に寄り添い、幸せな住まいづくりのサポートをすることに充実感を覚えました。
また、学生時代に必死になって自分と向き合った時間、例えば友達との関係の中で「ノー」と言えない状況や、何かを考え抜かなければならない場面が、結果的に自分を知るチャンスになりました。そこで新しい自分を発見し、それを受け入れることができたのです。他人の評価を気にせず、自分が「こうやりたい」と思うことを素直にやれば、それが自分らしくいられることにつながると気づきました。
環境の変化を恐れず、むしろ楽しむマインドセットは、そうした経験の中で自然と培われていったのかもしれません。
2.苦悩と挑戦が磨いた「人の心に寄り添う」仕事
―― その後は、どのようなキャリアを歩まれたのでしょうか?
実和さん:その後は人事部に異動し、人財開発に携わるようになりました。また、人権啓発やハラスメントの相談窓口を担当する部署では、グループ従業員が働きやすい職場づくりに取り組みました。これは非常に苦労の多い仕事でしたね。
ここでは、社員のキャリア研修など、モチベーションを高めるポジティブな業務と、社員一人ひとりの悩みや課題に寄り添い、ハラスメント相談というマイナスをゼロにする業務の両方を経験しました。この両面の仕事は、私のキャリアにおいて大きな基盤となりました。

―― マイナスをゼロ。相談業務は、心労も大きかったのではないでしょうか?
実和さん:はい、本当にそうでした。若い世代とベテラン世代でハラスメントの認識が異なったり、時代の変化と共に内容も複雑になっていきました。相談者の人生に深く関わる問題でもあるため、会社として責任ある対応が求められます。人と関わる仕事である以上、背を向けず、自分から真摯に向き合う姿勢を貫いてきました。
また、当時、この部署では、女性の相談窓口は私しかいなかったため、女性からの相談に対応する役割の重要性も強く感じました。従業員やお客様の多様な声に応えるためにも、組織の多様性を高めることが不可欠だと改めて認識しました。
この部署には約13年間在籍し、多くの悩みを抱える方々と向き合ってきました。個人で悩みを抱えてしまい、つらい時期もありましたが、ある時、上司に相談したところ、「それは個人で抱える問題ではない。会社の問題だから、組織で対応すべきだ」と言ってくれたのです。その言葉は、私にとって大きな救いとなり、非常に楽になりました。一件一件の相談に真剣に向き合いながらも、抱え込みすぎず、組織として対応したあとは「それはそれ」として手放すことを学びました。
―― その経験が、しなやかに生きる術として実を結んだのですね。
実和さん:まさに、実践の中でしなやかに生きる術を学んでいきました。ネガティブな状況に飲み込まれないよう、どう切り抜けるかを試行錯誤した日々でした。
ただ、私の場合、何かを深く考え続けたからというよりも、岐路に立った時に、上司や同僚に恵まれ、相談できる環境があったことが大きかったです。そこで自分の進むべき道を考え、選択し、行動することを繰り返してきました。意思決定の重みが増す中でも、「それはそれ」と受け止めることができたり、「あの人もできるのだから、私もきっとできる」と思えるのは、周囲の方々の存在や支えがあったからだと思います。
――今の役割に変わったのはいつからですか?
実和さん:2020年にダイバーシティ推進部の責任者として異動することになりました。私にとっては衝撃的で、会社にとってもサプライズ人事だったと思います。
それまで課長職で、大きなマネジメント経験もありませんでしたし、この役職は会社の経営戦略上、非常に重要な位置づけでした。特に、ESG(環境・社会・ガバナンス)の社会性向上部会長を兼任することになり、投資家対応なども求められるようになりました。自分の発言が会社の経営を左右するという、これまでにない大きなプレッシャーを感じました。初めて眠れない夜を経験し、「役員になるってこういうことなのか」と痛感しました。
しかし、ここでも身近に相談できる上司がいて、私が悩んでいると「それでいいのよ」「悩むということは成長につながること」と、全てを肯定的に受け止めてくれました。その言葉に支えられ、また目の前のことに一生懸命取り組みながら、自分の役割を果たすことに精一杯尽くしてきました。
振り返れば、そうして一歩ずつ着実に進んできた結果が、今の自分を形作っているのだと思います。

3.三つの哲学で導く心豊かな人生
―― 実和さんがキャリアを築く上で大切にしてきた、根底にある考え方について、もう少し詳しくお聞かせください。
実和さん:実和さん:はい、私が大切にしていることが三つあります。一つ目は「インナーダイバーシティ(内なる多様性)」です。これは、以前人権の業務をしていた時に他社の尊敬している方から教わった考え方なのですが、自分自身の中に多様性がなければ、他者の多様性を受け入れることができないというものです。だからこそ、自分の枠を広げるために、苦手なことに挑戦したり、知らないことにも目を向け、さまざまな経験を積むことが大切だと考えています。
「多様性」を広げるためにはたくさんの「役割」を持つことが重要です。例えば、あるコミュニティではある役割、別のコミュニティではまた違う役割、家族の中での役割など、さまざまな居場所を持つことで、自分の多様性が広がり、どこかで辛いことがあっても、別の場所では救われるという「サードプレイス」のような考え方にもつながっています。
また、自分自身で「これはできる」「これはできない」と天井を決めてしまうことが最も大きな壁になると感じています。人から与えられる壁は乗り越えられても、自分で作った壁はなかなか壊せない。だからこそ「ジョハリの窓」のように、自分の窓を意識して開いていくことが非常に重要だと考えています。
―― 自分自身で限界を作らない、ということですね。二つ目の哲学は何でしょうか。
実和さん:二つ目は「ウィークタイズ(弱い繋がり)」です。
親戚や家族や親しい友人といった、価値観の近い人たちとの「強い繋がり」はもちろん大切ですが、年賀状だけの関係や、小学校・中学校の友達、たまにしか会わない人など、価値観が異なる「弱い繋がり」からも多くの学びが得られます。異なる考え方に触れることで、自分の思考が広がり、新たな気づきが生まれます。たくさんの人とのコミュニティを持つことが、結果的に幸せにも繋がると考えています。
―― そして三つ目の哲学は。
実和さん:三つ目は「意思を持って楽観的でいると決める」ということです。
私たちは、行動だけでなく、自分が今どんな気持ちでいたいのかを選択することができます。意識的に選択せずに、自然に任せていると、先のことを心配したり、過去を後悔したりと、ネガティブな感情に流されがちです。
ただ、これは「何も考えずに楽観的でいればいい」という話ではありません。物事には表と裏、光と影があり、どの側面を見るかによって、結果も価値観も感じ方も変わります。自分がどちらに光を当てるか、意識的に選択することが大切です。変化を恐れず、むしろチャンスと捉え、楽しむというマインドセットもここから生まれています。

――変化を楽しむというマインドセットは素晴らしいですね。では、実和さんにとっての「生きがい」とは、どのようなものでしょうか。
実和さん:積水ハウスには、相手の幸せを願いその喜びを我が喜びとするという企業理念の根本哲学「人間愛」と、“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンがあります。私は「幸せ」という価値基準を持つことで、物事の判断がとてもシンプルになると考えています。何か言葉を発する時、行動する時、「これは相手にとって幸せか?」「自分にとっても幸せか?」という視点で考えるようにしています。ハラスメントの相談業務でも、「どこまでがパワハラなのか」と境界線を探るよりも、「それは幸せかどうか」というシンプルな問いで判断するようにしていました。
会社の考える「幸せ」の要素は「健康、つながり、学び」の三つです。その中でも、私にとって一番大切だと感じるのは「つながり」です。人は一人では生きていけません。人とのつながりの中で学び、成長していくものだと思っています。家族、友人、会社の仲間、仕事を通じて出会った人々との繋がり、そしてそこから生まれる議論や異なる視点こそが、私を成長させてくれると感じています。単なるインプットではなく、現場での経験から得られる学び、それはまさに「プランドハップンスタンスセオリー(計画された偶然)」のような考え方が根底にあります。
ーー 最後に、これからの「実和さん」として、どのような未来を描いていらっしゃいますか。
実和さん:私は、「女性としてこうなりたい」というような性別にとらわれたビジョンを持っているわけではありません。ただ、周りには素敵な先輩方がたくさんいらっしゃり、人生にはさまざまな選択肢があることを示してくださっています。
今の私があるのは、周りの人々のおかげだと心から感謝しています。だからこそ、私も「後に続く人たちが少しでも生きやすくなるような存在」でありたいと思っています。前の世代の方々が切り開いてくださった茨の道を、私はもう少し、その道を「綺麗に整えて」、皆が通りやすくしてあげたい。心豊かに、感性豊かに過ごし、これからも人との出会いや繋がりを大切にしながら、人間力を高めていきたいと思っています。
取材後記

目の前の仕事に真摯に向き合い、自身の役割を見出して道を切り開いてこられた実和さん。学生時代から人々の「相談役」として課題を解決し、喜びを引き出す原動力とされることで、与えられた職務を超え、自ら価値を発揮する姿勢を貫いてこられたとおっしゃる変化を恐れず「しなやかで快活な生き方」が印象的でした。
実和さんのこうした働き方・生き方は、私たちに働くが自身のIKIGAIの実現機会と捉える勇気、仕事が豊かな人生の源となるようなワクワクする「幸せ選択」の可能性として、後進に背中を見せてくださる姿に勇気をいただくインタビューとなりました。
【企業データ】
会社名:積水ハウス株式会社
事業内容:戸建住宅事業、賃貸・事業用建物事業、リフォーム事業、国際事業など
所在地:〒531-0076 大阪市北区大淀中一丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト
資本金:203,300百万円
従業員数:15,664名 (2025年1月31日現在)