

人が主役のものづくり。想いが育む「共にある」文化(葵機工株式会社)
精密な金属加工技術で、日本の自動車産業をはじめとする基幹産業を支える葵機工株式会社。その強さの源泉は、140台もの設備が24時間稼働する生産体制だけではありません。同社は「健康経営優良法人(ブライト500)」に認定されるなど、社員一人ひとりの心と体の健康に深く向き合っています。しかし、その取り組みはトップダウンの制度として始まったのではありませんでした。会社の未来を想う社員たちの自発的な声に、経営者が真摯に耳を傾ける。そこから生まれた小さな活動の輪が、やがて組織全体を巻き込み、明るい文化を育んでいく。これは、管理や評価だけではない、人と人との繋がりを信じる「場の経営」の物語です。

葵機工株式会社:左から順に 山中 治 さん(常務取締役)、佐々木 弥香 さん(総務部係長)、小禄 優美 さん(品質管理課係長)
1.自立経営で磨く製造力
――まず、御社の事業についてお伺いしたいのですが、親会社であるサンコー株式会社様との関係性が非常にユニークだと感じました。一般的なグループ会社とは少し違うのでしょうか?
山中 治さん(以下、山中さん): そうですね。私たちはネジなどを扱う商社であるサンコーのグループ会社ですが、経営は基本的に独立しています。商社の製造子会社というと、親会社が受注した仕事の生産を担うイメージが強いと思いますが、私たちは自社で直接お客様を持ち、独自の事業を展開しています。親会社の仕事は多くはありません。これは、景気の波に左右されず、自分たちの足でしっかりと立つための、先代からの経営方針なんです。
――なるほど、互いに依存するのではなく、それぞれが自立しながら支え合う関係なのですね。
山中さん: その通りです。親会社が困った時には私たちが技術で支え、私たちが厳しい時には親会社が支えてくれる。そうやって、お互いの強みを活かしながらシナジー効果を生み出していくことを目指しています。
――御社の技術的な強みは、どのような点にあるのでしょうか?
山中さん: 私たちの主力事業は、自動車のエアバッグ関連部品やターボチャージャーの重要部品といった、高い精度が求められる金属の切削加工です。特に強みとなっているのが、その生産体制です。CNC自動旋盤という設備を140台保有しているのですが、これだけの規模を持つ会社は国内でも珍しいと言われます。そして、24時間のうち16時間は完全に無人で設備を稼働させることで、高い生産性を実現しています。これが私たちの大きな強みですね。

――140台の設備と無人稼働体制。それが高い品質と生産性を両立させているのですね。
山中さん: はい。エアバッグのような人命に関わる部品は、ほんの少しのバリ(加工時にできる突起)があっても誤作動に繋がるため、品質管理には非常に厳しいものが求められます。そうした要求に応え続けてきたことで、お客様からの信頼をいただき、口コミで新しいお付き合いが始まることも少なくありませんでした。
2.女性たちの想いが組織を動かした
――そうした技術本位の「ものづくり」の会社が、なぜ「健康経営」という「人」に焦点を当てた取り組みを始めることになったのでしょうか?
山中さん: 実は、直接的なきっかけは創業50周年を機に進めたホームページのリニューアルでした。2021年頃ですね。
佐々木 弥香さん(以下、佐々木さん): はい。各部署から若手を中心にメンバーが集まり、会社の魅力をどう伝えていくか話し合う中で、総務部としてCSR(企業の社会的責任)の側面をどうアピールしようかと考えました。その時に「健康経営」というキーワードを見つけたんです。

――最初から健康経営を目指していたわけではなかったのですね。
佐々木さん: そうなんです。調べてみると、会社が費用を負担してくれている健康診断やインフルエンザの予防接種、毎日のラジオ体操の推進など、すでに私たちが当たり前にやっていることが、健康経営の取り組みに当てはまると気づきました。「これなら、もっと発信していけるんじゃないか」と、そこから本格的に活動が始まりました。
――そこから、どのようにして全社的な取り組みへと発展していったのでしょうか。
山中さん: しばらくして、女性の役職者たちから「自分たちが中心になって健康経営を推進したい。会社に何か自分たちの手でやったことを残したい」という声が上がってきたんです。これは嬉しい驚きでしたね。会社としての方針はありましたが、それを自分たちのこととして捉え、形にしたいという想いを持ってくれた。それならばと、「君たちで健康経営を形にしていってほしい」と全面的に任せることにしました。
小禄 優美さん(以下、小禄さん): 最初は6人からスタートしました。今では1人増えて7人のチームで活動しています。本社だけでなく、愛媛の工場など複数の拠点があるので、どうしてもコミュニケーションが取りにくいという課題がありました。健康経営の活動が、その拠点間の壁を越えるきっかけになればいいなという思いもありました。
佐々木さん: 最初の1年間は、本当に手探りでした。「何をしようか」「どうやって進めようか」と、みんなでアイデアを出し合いながら、試行錯誤の連続でしたね。自分たちの通常業務に加えての活動なので、もちろん大変な時もありますが、みんなで協力しながら進めています。
3.イベントが育んだ明るい職場と新しい風
――具体的な取り組みについて教えてください。どんな変化がありましたか?
山中さん: 大きな変化のきっかけになったのが、健康診断にプラスして始めた体力測定です。握力測定なんて、社会人になってからやる機会がないでしょう。これが意外にも盛り上がって、社員たちが自分の身体や健康に興味を持つきっかけになったんです。
小禄さん: そこから、年に1回のイベントを企画するようになりました。最初は「しまなみ海道サイクリング」。個人ではなかなか行けないけれど、会社のイベントなら参加してみようという人が集まって、家族も含めて20人くらいで走りました。その後もボーリング大会やプチ運動会などを開催し、今では50人規模のイベントになっています。

佐々木さん: イベント後には必ずアンケートを取るのですが、「楽しかった」という声が次のイベントへの参加者を増やしてくれています。普段は仕事でしか関わらない人たちの違う一面が見えたり、拠点を超えて話すきっかけが生まれたり。活動を通じて、間違いなく会社全体のコミュニケーションが活発になり、雰囲気が明るくなったと感じています。
――ものづくりの現場は、黙々と作業するイメージがありますが、雰囲気が変わったのですね。
山中さん: ええ。どうしても技術職の人間が多く、コミュニケーションが活発とは言えない雰囲気がありました。以前からもう少し風通しを良くしたいという思いがあったのですが、彼女たちの活動がその空気を大きく変えてくれましたね。こうした変化は、採用活動にも良い影響を与えています。会社の良い雰囲気が伝わるのか、近年は若い新入社員も継続的に入ってきてくれるようになりました。
佐々木さん: 採用は簡単ではありません。特に高校生の採用では、多くの企業が学校を訪問するので、先生になかなか会ってもらえないこともあります。それでも、卒業生を連れて行って今の仕事の様子を話してもらうなど、地道な活動を続けることで、少しずつ会社の名前を知ってもらえるようになってきました。会社の雰囲気が良くなっていることは、学生さんにもきっと伝わると思っています。
4.常務が語る、人と技術が響き合う未来
――山中常務ご自身の経営における想いについてもお聞かせください。SNSなどを活用しない方針も、何かお考えがあってのことでしょうか。
山中さん: 私は、最終的には「顔を見て話す」ことが一番大事だと考えています。コロナ禍でウェブ会議が主流になりましたが、やはり画面越しでは伝わらない情報、引き出せない本音があります。お客様のところに足を運ぶからこそ「ここだけの話」が聞けるし、困った時に助け合える人間関係が築けるんです。SNSは手軽ですが、その手軽さが薄っぺらさにも繋がりかねない。私はそういうのがあまり好きではないんです。
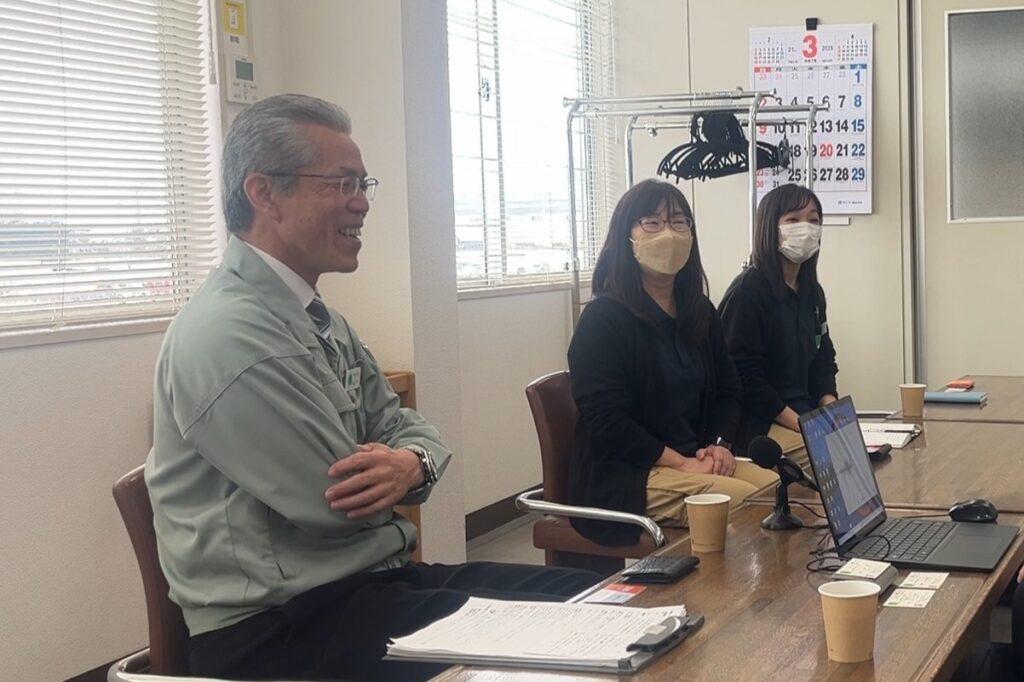
――その「人と人との繋がり」を重視する想いは、働き方にも反映されているのですね。
山中さん: 先ほどお話ししたように、うちの強みは16時間の無人稼働です。だから社員には、「8時間の中で、残りの16時間を動かすための準備をやり切ってほしい」と伝えています。残業を当たり前にするのではなく、本当に必要な時は理由を明確にして申請する形にしました。そうすると、どこで問題が起きているのか、誰に負荷が偏っているのかが見えてくる。それは現場を改善するための貴重なヒントなんです。
――会社の未来については、どのようにお考えですか?
山中さん: 私たちの加工技術は、海外でも真似できるかもしれません。しかし、材料メーカーや設備メーカー、そして同業者と連携しながら、お互いの知恵を出し合って作り上げてきた「トータルの技術」は、簡単にはコピーできません。私は、こうした日本のものづくりの強みである「横の連携」をもっと広げていきたい。困った時に「葵機工に相談すれば何とかなる」と思ってもらえるような、よろず屋的な存在でありたいですね。
――技術だけでなく、ネットワークそのものが強みになる、と。
山中さん: そうです。結局、経営も「人づくり」であり、技術も人がいてこそ磨かれる。その想いを大切に、これからも歩んでいきたいですね。
取材後記
今回の取材で強く感じたのは、葵機工の強さが、制度ではなく、社員の内側から生まれた純粋な「想い」を起点としている点です。経営者が「会社のために何かをしたい」という社員の声を信じて任せたこと。その想いが、部署や拠点を超えて人と人とをつなぐ温かい「場」を生み出し、組織全体に活気と一体感をもたらしました。
まさにこれこそが、一人ひとりのIKIGAIを中心に据え、個人の幸せと組織の持続可能性を同時に実現するIKIGAI経営の実践と言えるでしょう。葵機工の物語が教えてくれるのは、小手先の施策ではなく、社員一人ひとりの「やってみたい」という情熱を大切に育むことこそが、最も強く、持続可能な組織をつくるという経営の普遍的な真理です。認定は、その結果として自然についてきた勲章に過ぎないのでしょう。
【企業データ】
会社名:葵機工株式会社
事業内容:精密部品製造(CNC自動旋盤による金属切削加工)
所在地:〒760-0065 香川県高松市朝日町3丁目7−5
資本金:25百万円
従業員数:120名




