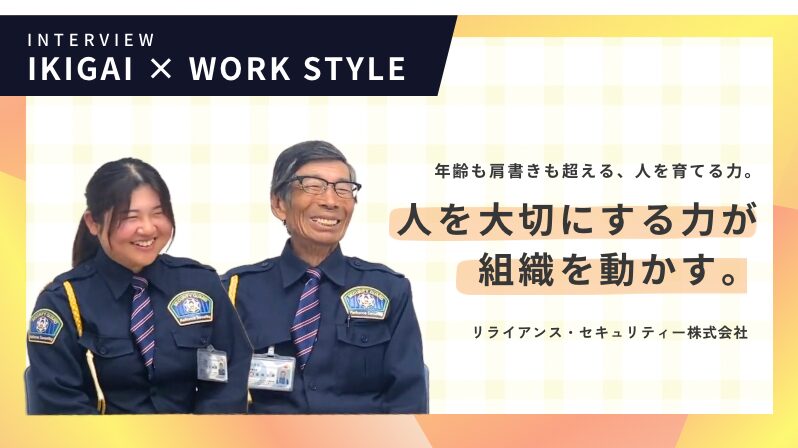情熱で築く、地域と従業員の未来への架け橋(株式会社平山組)
長崎県大村市に根ざし、地域を支え続けてきた平山組。中村専務は、会社を単なる組織としてではなく、社員一人ひとりが自分らしく働き、生きる喜びを見出す「場」として捉えています。評価や競争に追われがちな現代社会の中で、専務は「心の内側から湧き上がる安心感」と「人と人とのつながり」を大切にしています。そんな独自の働き方と、社員と共に未来を切り拓くその想いを伺いました。

株式会社平山組:中村友久さん(専務取締役)
1.異色のキャリアが拓いた、家業を継ぐ道
――本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。早速ですが、御社の事業内容について、簡単にお聞かせいただけますでしょうか?
中村 友久さん(以降、中村さん):はい、株式会社平山組は総合建設業というジャンルでして、土木・舗装・建築の3工種を中心に、公共工事から民間の建物や道路、駐車場などを幅広く手掛けさせていただいております。現在(2025年3月)、従業員は37名ですが、4月にはさらに6名が加わり、43名になる予定です。大村市は今後も公共工事の発注が見込まれるため、新卒採用に力を入れ、人材育成に注力しています。
――御社は1929年創業と、非常に長い歴史をお持ちですね。元々はどのような事業から始まったのですか?
中村さん:私のひいおじいさんが始めたのですが、当時は土木業が中心でした。戦時中に国鉄(現在のJR)の線路を島原に通すプロジェクトがあり、その土地を所有していた方と協力して土木事業を始めたのが会社の原点です。ひいおじいさん自身の人生もとてもドラマチックでした。旅役者の一座に加わって家を飛び出し、熊本での興行先で出会った地主の娘と駆け落ち。その後、島原で事業を立ち上げたのです。

――そうなんですね!ひいおじいさんのチャレンジ精神や行動力が、今の中村さんの原点にも繋がっているように感じます。中村さんご自身は、どのようにして御社に入社されたのですか?
中村さん:私は大学では法学部に進み、工業系の学びとはまったく無縁でした。高校時代からバンド活動に熱中していて、その夢を追いたくて関東の大学に進学したんです。卒業後もフリーターをしながら音楽活動を続け、25歳になるまで建設業には一切関わっていませんでした。25歳の時、地元に戻ることを考えた際に「どうせなら実家の会社で働いてみたい」と思い、親にお願いして入社させてもらったんです。
――全く異なる分野から家業に入られたのですね。最初からスムーズに経営に携われたのでしょうか?
中村さん:いえ、それが当初は全く違いましたね。20代で会社に入った頃は、社会人経験こそなかったものの、アルバイトやフリーターとしての経験から、もっとシンプルに、スマートに、的確に仕事を進められるはずだという思いがありました。地方の中小企業には無駄が多く、手書きとパソコンで二重に管理している業務など、改善できる点がたくさん見えたんです。私はパソコン業務への移行やペーパーレス化を提案しましたが、周りからは「そんなのできるわけない」と、ほとんど却下されていましたね。
――それはもどかしかったでしょうね。どのように乗り越えられたのですか?
中村さん:30代になってからは、青年会議所や法人会青年部など、社外の活動に力を入れるようになりました。同じ年代の異業種の方々と交流する中で、たくさんの刺激を受け、そちらの活動が楽しくて、会社にいる時間よりも外部での活動が多かったですね。会社を「こうしたい」という提案は、この時期はほとんどありませんでした。
潮目が変わったのは、2019年から2020年にかけてのコロナ禍です。社外活動が軒並み縮小し、会社にいる機会がぐっと増えました。そこで会社を見渡すと、「ここは働きづらそうだな」とか「もっと良くできるな」という点が見えてくるようになったんです。巷では働き方改革という言葉が出始めていましたが、具体的に何をすればいいのか、皆が分からずにいました。そんな時、健康経営の取り組みに出会いました。
2.「場」を耕し、社員の「働く意味」を育む
――コロナ禍を機に、会社の内側に目が向くようになったのですね。健康経営への取り組みは、働き方改革にどのように繋がったのでしょうか?
中村さん:はい。健康経営は、従業員の健康を守る尺度を満たせば国の認定がもらえる制度なのですが、お金をかけずにできることが多かったんです。自分たちがすでにやっていることも加点対象になることが分かり、足りない部分を補うことで、「来年はこれをクリアしよう」という目標ができました。その目標をクリアするために会社で何をするか、という具体的な行動に落とし込んでいくと、結果的にそれが働き方改革に繋がっていくことに気づいたんです。

働き方改革を直接的に進めようとすると、抽象的で皆が戸惑うのですが、「健康になるために」「より健康に働くために」という明確な目的があれば、年齢に関係なく誰もが意識できます。そうすることで、働き方はスムーズに進んでいくと感じました。
――なるほど、「健康」という誰もが共感できる軸が、改革を推進するきっかけになったのですね。社員の方々の反応はいかがでしたか?
中村さん:非常に協力的でしたね。例えば、ガラケーからスマートフォンへの移行を進めた時も、高齢の社員の中には使い方に戸惑う人もいましたが、若い社員に「分からないから教えてください」と声をかけ、一緒に設定してもらう姿が見られました。年配の社員が感謝し、喜んでいるのを見て、改めて「うちの従業員はとても素直で、思いやりがある」と感じました。そういった社風があるからこそ、新しいことにも皆が協力してくれるのだと思います。これは、すぐに手に入れることのできない、脈々と受け継がれてきた当社の財産だと感じています。
――まさに御社の「人」が強みになっているのですね。御社の経営スタイルについても伺いたいのですが、社長や中村さんご自身は現場に出られるタイプではないとのこと。社員の方々をどのように支え、動機付けているのでしょうか?
中村さん:そうですね、私の父である社長も私も、現場にバリバリ出ていたタイプではありません。私たちの役割は、社員が最前線で頑張れるような「環境作り」や「場作り」に徹することだと考えています。従業員には「最大限に会社を利用して、自分の人生を豊かにしてください」と伝えています。
今は、書類作成を専門とする部署を設け、現場監督がコア業務に専念できるようにしています。また、今後は外国人技能実習生が加わり、作業分担も進める予定です。そうすることで、皆が定時で帰宅でき、ワークライフバランスの整った従業員が増える状態を作りたいと考えています。また、DX推進室を立ち上げ、システムエンジニアの経験を持つ弟にDX推進を一任しています。これにより、業務効率化が一層進みました。

――社員一人ひとりの働きがいや、人生の充実までを考えられているのですね。ベテランの職人さんたちが培ってきた技術や経験は、今後どのように活かされていくとお考えですか?
中村さん:建設業はこれまで「背中を見て覚えろ」という文化が強かったのですが、今の若い世代は1から10まで教えてあげる必要があると、ベテランも気づき始めています。しかし、教え方が分からないという課題もあります。今後は、既存の従業員も「どう教えたら伝わるか」「どうコミュニケーションを取るか」を学ぶ必要があると考えています。
一方で、テクノロジーが進化する中で、人間が全てを担う必要はないとも感じています。AIやDXに任せられる部分はどんどん委ねて、人間は人間しかできないことに注力していくべきです。当社のベテラン社員は、公共工事で培った「カチッと決められた仕様を正確に、高品質で作り上げる能力」が非常に高いという強みがあります。この強みを活かしつつ、彼らの経験や知恵を、新しい技術と融合させていくことが重要だと考えています。
3.地域と共に築く、社会と響き合う未来
――時代を見据え、ベテランと若手が協働する未来像ですね。御社は100周年を迎えるにあたり、新たな企業理念も策定されたそうですね。その想いについてお聞かせください。
中村さん:はい、95年目を迎えるにあたり、「一歩先行く建設業のかたちになる」というビジョンを掲げ、企業理念をアップデートしました。これは、単に大規模な建設業を模倣するのではなく、大手企業が取り組む成功事例や失敗事例を参考にしつつ、私たちが独自の強みとして「現状よりあと一歩だけチャレンジしてみる」エネルギーを皆で使っていこうという想いが込められています。今の若い世代が会社を選ぶ際、明確で分かりやすい理念は非常に重要だと感じていますので、この理念を通じて「平山組で働いてみたい」という気持ちを育みたいと考えています。
私自身、常にワクワクしていたいタイプで、挑戦することが好きなんです。働く時間は人生の3分の1を占めるので、苦痛を感じるのではなく、楽しく転換できる場所を探すべきだと思っています。平山組がそういった環境を提供し、社員が最大限に会社を利用して自分の人生を豊かにしてほしいと願っています。
――「一歩先行く」というビジョンには、中村さんのワクワクする気持ちが反映されているのですね。地域との関わり方についても、新たな構想があるとお聞きしました。
中村さん:はい。建設業界は人材確保が課題であり、地方の中小企業は特に苦戦しています。人材紹介に高額な費用を払うだけでは根本的な解決にはなりません。そこで、私たちが「物作りのプロフェッショナル」として、地域のプロフェッショナル(農業、林業、水産業、行政など)と連携し、地域の課題解決に取り組むことが重要だと考えています。
具体的には、現在計画していることが二つあります。一つは「アップサイクルリノベーション」のブランディングです。大村市は人口が増加していますが、土地が不足しています。しかし一方では空き家問題が今後深刻になっていきます。そこで、空き家を単なる再利用ではなく、「よりよく暮らす形に変える」アップサイクルリノベーションを推進し、地域の風土に合った建物の再生を目指しています。これにはベテラン職人の経験やノウハウが不可欠です。
もう一つは、100周年に向けて、山を買い取り民間運営の公園を作る構想です。これは行政が作る公園とは異なり、市民の声が反映されやすい「皆で育てる公園」を目指します。総合建設業なので土木、舗装、建築の全てを活かし、部署を越えて社員が一丸となって取り組む、良いきっかけになると考えています。大村市には大きなアミューズメント施設が不足しており、こうした公園を通じて地域の娯楽や文化の課題解決にも貢献したいです。
――それは素晴らしい構想ですね。地域の課題解決が、御社の新たな事業の軸になるのですね。しかし、こうした取り組みはすぐに収益に繋がらない部分もあるかと思いますが、その点についてはどのようにお考えですか?

中村さん:おっしゃる通り、こうした活動はすぐに損益計算書に反映されるわけではありません。しかし、従業員の成長、地域の方々からの感謝、エンゲージメントやロイヤルティの向上といった「見えない資産」として、着実に会社に蓄積されていくものだと考えています。
例えるなら、毎日の食事や生活習慣のようなものです。好きなものだけを食べたり不規則な生活をしていても、すぐに体調を崩すわけではありませんが、長い目で見れば必ず差が出てきます。一方で、栄養を意識した食事や適度な運動を続けていけば、時間をかけて確実に体調や見た目に良い変化が現れ、健康という大きな成果に結びつきます。
目先の利益だけを追うのではなく、当社のような歴史と資産を持つ企業が、地域社会と共に未来を創造する姿勢を示すことで、長期的には必ず収益に繋がると信じています。
社長も、一方的に決めるのではなく、従業員や役員の声を取り入れ、共に未来を描いていく。その姿勢を理解し後押ししてくれています。特に新卒で入社する社員とは、私が企業説明会や面接から関わり、1年間教育担当も務めているので、私の想いが伝わりやすいと感じています。これからは、ベテラン社員にも、こうした地域貢献や社会とのつながりが、会社の成長や彼らの仕事の意味にどう繋がるかを丁寧に伝え、共感を広げていきたいと考えています。
――なるほど。まさに、目に見えない価値を創造していくことが、御社の持続的な成長の原動力になるのですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。
取材後記
中村さんへのインタビューを通じて、彼がいかに「人」と「地域」に深く向き合っているかを強く感じました。彼の言葉からは、社員を単なる「成果のための人材」ではなく、共に働く家族のような存在として大切にする想いが溢れていました。
健康経営から始まった働き方改革、そして今構想している地域課題解決型の新規事業は、全てが「社員一人ひとりが自分らしく輝ける場を創りたい」という彼の揺るぎない願いに繋がっています。中村専務の「ありのままの自分」を肯定し、地域や社員との関係性の中で意味を紡ぎ出すIKIGAIある人生の実践から、自身の働き方や生き方を見つめ直す勇気と示唆をいただきました。
【企業データ】
会社名:株式会社平山組
事業内容:建築工事の設計・施工・管理/土木工事の設計・施工・管理/舗装工事の設計・施工・管理/下水道工事の設計・施工・管理/鉄道工事の施工/アスファルト合材販売/不動産関連事業
所在地:〒856-0826 長崎県大村市東三城町8-4(本社)
資本金:30百万円
社員数:43名